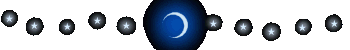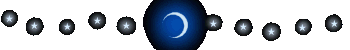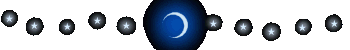|
リュウセイは最近、ライがまるで自分の母親のように思える時がある。
そう思う時には二通りあるのだが、例えばそれは─
ちょうど、今のような時。
「こら、リュウセイ。何度言わせる気だ?食べる時には足を立てるな。肘をつくな。…これは日本の作法だぞ。」
今は夜。
訓練も終わって夕食を取っている所だが、生憎食堂の席は満員状態。
仕様がないのでトレイに定食を乗せてもらってそのまま外で食べる事にした。
リュウセイが、やたらと外にこだわった為でもある。
今日は春らしい暖かないい天気で、風もそんなに強くはない。
そして何よりも、とてもいい月が出ているのを、彼が帰り際に見つけてしまったから。
そういった事情もあって、二人で―
―アヤはイングラムと何やら話があるということで一緒に来れなかった―
―二人で、極東支部の屋外休憩所、中庭のような所に来ているのだが
リュウセイにとっては月見所ではなくなってしまった。
比較的大きな木の根元に並んで座っているのだが、その姿勢が悪いとライの説教が始まったのだ。
「いいじゃねぇか!誰が見てるわけでもねぇし、飯ぐらい好きに食わせてくれたって…」
「俺が見ている。
それに姿勢が悪いと言う事は体に良くない。習慣付いてしまうと内臓にも負担が……」
言い訳を途中で遮られ、リュウセイは口をへの字に曲げながら心の中で毒づいた。
……また始まった。
ホントにライはうるせぇんだよなぁ。
いっつも重箱の隅つつくようなトコばっか見つけてさ。…俺の事本当は嫌いでいじめてるんじゃねぇのか?
だが、そこまで考えてライへの悪口は止まってしまった。
そうではない事を一番良く知っているのは自分自身。全部、自分の為だと解っている。
ライがうるさいのは、本当に細かい事が命取りになる事があると知っているから。
しかし、それなら、と、不思議に思う事がある。
逆に、ライが自分以外の人間に細々しく注意している所を見掛けた事はない。
仲良くしてもらっている技術者や、ライの事を多少は知っているであろう人々に
「ライがいつも口うるさくて困る。」
というような事を話すと、ほぼ全員同じような反応をする。
ええっ!と、目を見開いて思い切り驚いた顔をしてくれるのだ。
「彼は他人に進んで干渉するような人間ではない」と。
ライがこんなに言ってくれるのは自分だけなんだろうか。
そう思うと、怒られているというのになんだか嬉しくなってしまう。
だからいくら言われても直らないんだ―などと言ったら、ライはきっとおかしな顔をするだろう。
急にニヤニヤし始めたリュウセイにライも張り合いがなくなったのか、小言は終わったようだ。
その代わりにリュウセイの顔をさしながらこう続ける。
「ほら、変な食べ方をするから…頬に飯粒がついている。」
いくつだお前はと言いながら心底呆れているようだ。
「え!うそ、どこ?」
と、リュウセイは自分の顔を袖で擦るがどうも見当違いの所ばかりに触っているようで
全く取れた感じはしない。
むぅ、と腕を組んでうなってからリュウセイはライの方を向いた。
「なぁライ、…鏡とかって持ってねぇ?」
それを聞いたライは「本当にお前は…」などとと言いながら、凭れていた木から少し腰を浮かせて向き直り
そっと、リュウセイの方へ右手を伸ばしてきた。
「……へ?ライ…何すんの?」
「取ってやるからおとなしくしていろ。」
その言葉の意味を理解する間もなく、リュウセイの左側の頬にライの右手が添えられる。
どきん
と、リュウセイは自分の心臓の音が聞こえたような気がした。
ライが、いつもよりとても綺麗に見えたから。
月の青い光がライの髪ではじかれ、不思議な黄金色に見える。
まるで透き通った薄い布を被っているようだ。
青い、深く澄んだ湖のような瞳がリュウセイを写している。
その綺麗な鏡の中に目を大きくしている自分がいて、なんだか不思議な気分になった。
瞳がゆらめいていると思うのはのは気のせいなのだろうか。
本当に綺麗だなと、思わず見惚れている間に
ライの顔はリュウセイのすぐ間近まで迫っていた。
はっ、と気が付いた時にはもう視界からライの姿はなく。
その代わりに映っていたのは、夜の闇に目映く輝く黄金と、それと同じような色をしている天空の月。
その瞬間、ふわり、と
唇の前を暖かい感触が通り過ぎていった。
「…リュウセイ、こんなものも自分で取れないのか?まったく、もう少ししっかりしろ。」
いつもと変わらないライの声に急に現実に引き戻される。
でも、月の光を受けているライはやっぱり綺麗で
見ていると何故か顔が熱くなってくるのであんまり見ないことにする。
…さっきのは何だったんだろう?
…まぁいいやとリュウセイの頭脳は考える事をさっさと放棄してしまう。
まだ頬に触れているライの手が暖かくてとても気持ちがいいから。
なんだか、心臓がまだドキドキしているけれどそれすらも心地よく思う。
あんまり気持ちがいいから、目を開けたくない。
このまま寝たらライが困るかな、と少しは思ったが、
襲ってくる眠気には勝てなかったようだ。
こんな所で寝るな、とか、食器を返しにいくぞ、とか。
そんな言葉が遠くから聞こえてくるが
リュウセイにはもうどうでもいい事だった。
ライに触れられている時、
ライにくっついている時が好き。本当に気持ちがいいと思う。
他のどんな事よりも、今はこうしていられる時を大切にしたいと思う。
リュウセイは眠い頭でぼんやりと思う。
ライに甘えている、とは解っているが、変な所だけ甘やかすライも悪い、と。
厳しいくせにめちゃくちゃやさしくしてくれる時、そんな時にもどうしても母親を連想してしまう。
今も、ライはリュウセイからの返事がないと解ると
ため息をひとつつきながらも肩に頭を待たれさせてくれている。
きっと目が覚めたらまた小言を言われるんだろう。
でも、それでもいいや。
ライの顔見てたら小言なんて半分も聞こえてこねぇんだから。
ライが聞いたら頭痛を起こしそうな事を考えながらリュウセイの意識は遠のいていった。
リュウセイが気持ちよく眠っている間
ライが何故「あんな事」をしたか、と激しく悩んでいた事など、
党の本人は無論、知る由もなく。
そして、二人とも月など殆ど見ていなかったことに気がつくのは
次の日「昨日の月は綺麗だった?」とアヤに尋ねられてからだったという。
|